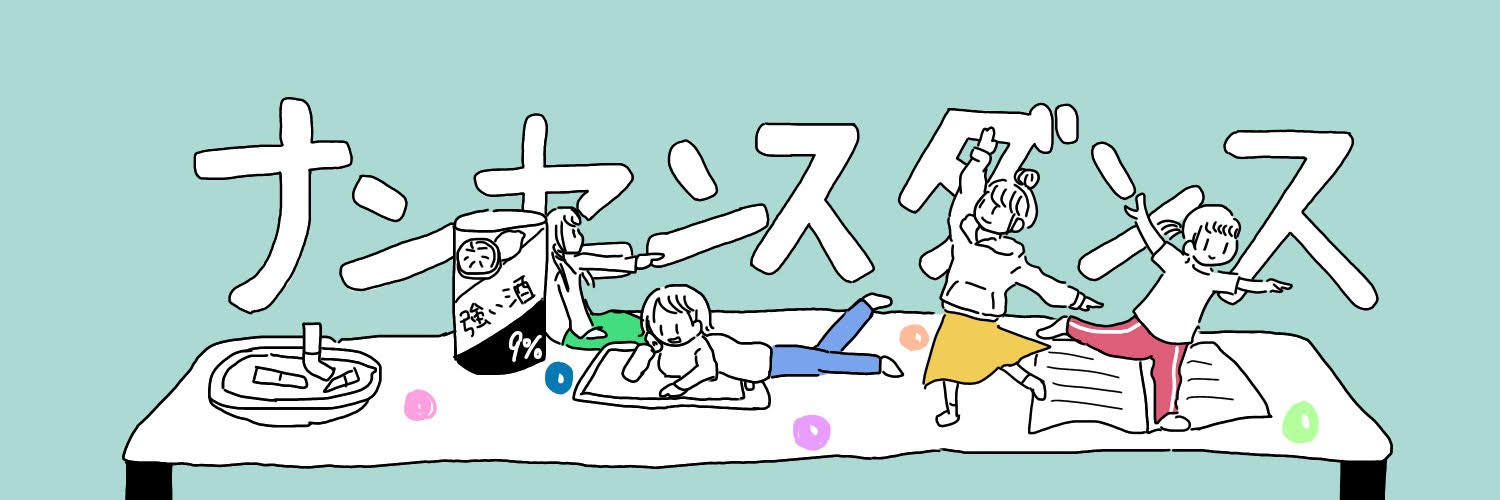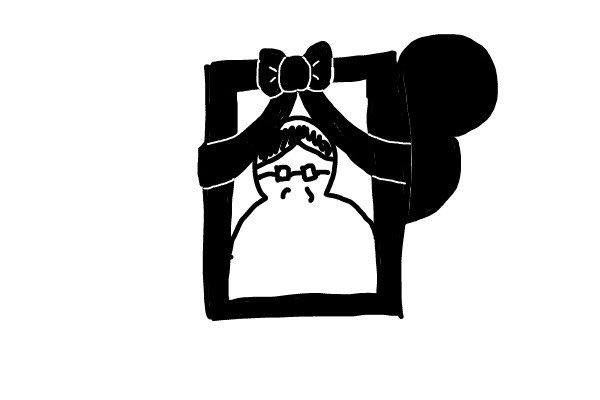最新記事 by ハンバ (全て見る)
- 父の死を語る - 2024-03-03
- 【祝】良い「はんだ」を見ながら酒を飲む - 2021-01-02
- 魔法少女パンりん「この先どうなっちゃうの〜〜!!」 - 2020-05-30
数年前に父が亡くなった。
まだ60にもならない父の死は衝撃が大きかった。
そろそろ区切りの法要なので、少し思い出に浸る。
母「とうとう緩和治療に入ったから、そろそろみたい。いつ帰って来れる?」
ハ「ちょっと週明けに仕事があるから火曜日に帰るわ。」
そんなLINEを週末にした。
『そろそろとは言われたけど、どうだろう。
あと1ヶ月くらいかな?』
『1ヶ月も東京にいるのか。まぁ、仕事はなんとかなるか』
そんなことを思っていた気がする。
月曜日には普通に出勤。
そこで初めて会社の上司にもしばらく東京に帰ると伝えた。
「看取りは子供にとっての重大な親孝行だから、ちゃんと一緒に過ごしてきなさい」
そう、部長には言われた。
火曜日にも普通に出勤。たまたま部長に会った。
部「お父さん大丈夫なのか?」
ハ「いや、本当にそろそろみたいです。この後すぐ帰ります」
部「出勤なんかしてないで早く帰ってあげなさい」
良い会社だと思った。
そりゃあ、父のそばにいない自分の事を親不孝だとは思っていた。
ただ、父自身も仕事人間だったので多分、自分のことも理解してくれるだろうとはなんとなく考えていた。
そうは言っても、定時ダッシュ決めてすぐに新幹線に飛び乗った。
『いつまで続くかわからない帰省が始まるぞ。』
そんなふうに思っていた。
♪〜
LINE電話が鳴る。
嫌な予感がした。発信者は母。
「たった今、お父さんの呼吸が止まりました」
あまりにも早すぎた。
あと1ヶ月くらいかと思っていたら、まだ自分は新大阪を出て名古屋にすら着いていなかった。
「わかった。」
しばらくは呆然としていた気がする。
ただ、不思議と涙は出なかった。よくある話だが、実感が全く湧かない。
そのまま新幹線で東京へ。実家に帰った。
そこには、家族と、眠ったままの父。
父はすでに葬儀屋さんによって死装束と死化粧が施されていた。
そんな父を目の当たりにして。
なぜか、泣きたくなかった。父に泣き顔を見られるのが恥ずかしいから。
家族はやっぱり号泣したらしい。
でも、自分と父はなんというか、親子でもあるけど1対1の大人として接してたような感じだったので、なんとなく親を失った悲しみというよりはお疲れ様みたいな、そんな感情の方が大きかった。
父の遺体を保護するために、ガンガンにクーラーの効いた部屋。
流石に寒かったので寝ずの晩なんかはせずに、実家を出た時のままにしていた自分の部屋で眠りについた。
あまりにも予想外。
死に目に会えなかったけど、会わなくて良かった気もする。
そんな考えもありながら、移動の疲れもあり比較的サッと気を失った気がする。
何時間か経った後。
ゴーっという凄まじい耳鳴りと共に目を覚ます。
なんだ?と思いながら目を開ける。
目を開けた瞬間、確かな違和感。
「体が動かない」
人生初の金縛りだった。
ゴーっという耳鳴りも止まず、体も動かせないまましばらくあたりを見回す。
ふと、視界の端に何かがいた。
よくよく見ると、髪の毛。
「えっ?」
そう思うとその頭部はゆっくりと自分の目の前に近づいてきた。

見知らぬ老婆だった。
どんどん近づいてくる老婆。
顔がはっきり見えるまで近づいてきた。
「やばい!!」
そう思い、渾身の力を振り絞って頭を持ち上げ、
老婆の鼻先に噛み付く。
粘土のような食感と共に鼻先を噛みちぎったような感覚。
そして、その瞬間に老婆は消え、金縛りも解けた。
慌てて体を起こして時計を見ると深夜2時。
いや、このタイミングで出てくるのは父であれよ。
そう思いながら再び眠りについた。
最新記事 by ハンバ (全て見る)
- 父の死を語る - 2024-03-03
- 【祝】良い「はんだ」を見ながら酒を飲む - 2021-01-02
- 魔法少女パンりん「この先どうなっちゃうの〜〜!!」 - 2020-05-30