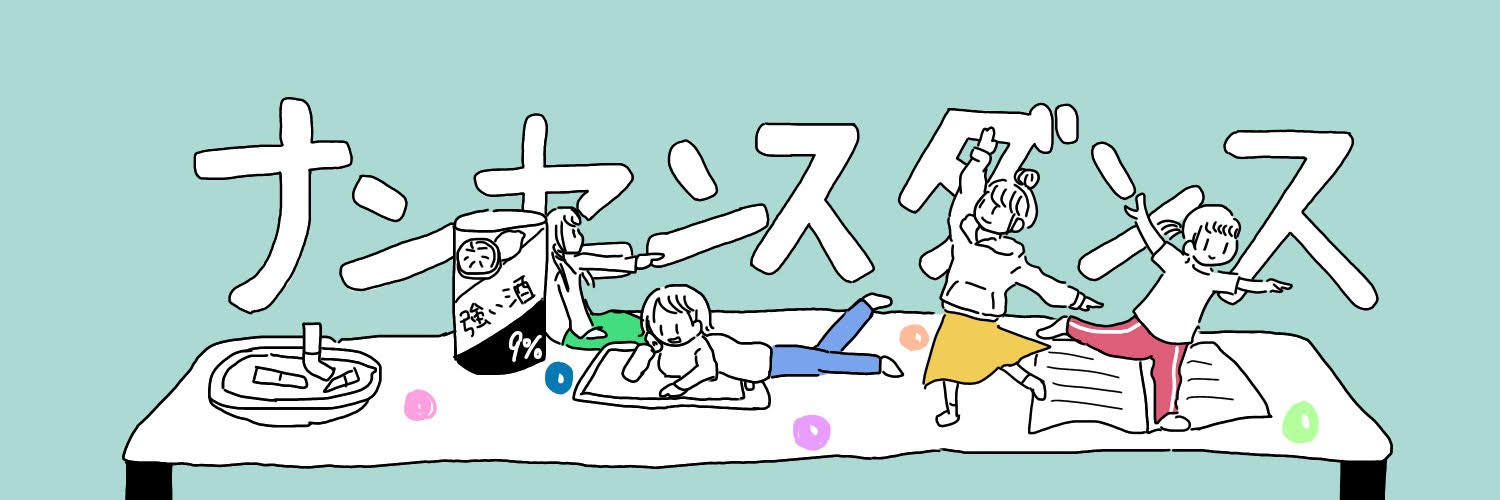最新記事 by DachimiN (全て見る)
- 【アメリカのモンスターエナジー徹底レビュー】結末に一同驚愕?!ガキが・・舐めてると潰すぞ!!! - 2021-01-03
- 地獄の免許合宿 ~外道も涙~ - 2020-10-28
- 人生で一番辛かったロシアンルーレット - 2020-08-26
はじめに
大学生の私は,これまでいくつかのアルバイトを経験してきた。そして,自分で言うのもおこがましいが,どんな環境でも職場の人と仲良くなれる傾向にあったと思う。
ジジイだらけの職場でも,自分以外全員女性の職場でも,それなりに上手くやってこれた自信がある。そんな中,最後まで仲良くなれなかった職場が1つだけあった。それは,お寿司屋さんのアルバイトだ。そこで経験した,世界一辛かったロシアンルーレットについてお話したい。
どれくらい仲良くなかったのか
自分がどれほど周りと馴染めていなかったかを端的に表す指標として,名前の呼ばれ方がある。アットホームな職場では,それぞれ下の名前(例:「マスオ!」,「ナミヘイ!」)やあだ名(例:「サブちゃん~」)で呼び合っていたが,自分だけ最後まで「名字+くん」(例:「イソノくん」)だった。一人だけ呼び方が違うというのはかなりの疎外感を感じた。
しかし,もちろんその程度で辞めようと思うクソザコゆとりではない。自分なりに彼らとの共通の話題を見つけようと模索した。しかし,話の大半は「パチンコ,競馬,S●X」で,アンパンマングミの新作を想像することで休日を過ごすような私にとって,こういった話題に合わせるのは容易ではなかった。したがって,みんなが盛り上がってる話に加わらずに,もくもくと仕事をすることが増え,それによってますます距離ができるようになってしまった。
多部未華子アツアツ事件
アウェーながら必死に働いていたある日,孤独を象徴する多部未華子アツアツ事件が起きた。店のキッチンには揚げ物をするフライヤーと呼ばれるものがあり,中の油を定期的に変えていた。その変え方は,古くなった油をキッチンの床にある排水溝に捨てるだけの簡単作業だが,非常に危険が伴う。というのも,床の排水溝はみんなが頻繁に通る動線上にあり,注意を怠るとうっかりアツアツの油の海に足を突っ込んでしまうことになるのだ。事実,アットホームな職場で超人気者のタラオくん(仮名)は,以前,足をつっこんでしまったことがあるらしく,後世まで語り継がれる爆笑テッパンネタとなっていたのだ。
ワイワイとタラオくんをイジる輪に入れないため,私は1人で可愛い客を視姦することに徹するのだが,ふとお客さんの中に多部未華子に似ている美人がいることに気が付いた。笑う時に手で口元を隠すしぐさや,誰かの話を聞くときは身を乗り出して耳を傾ける様子は非常に可愛かった。もっと近くで見たいと思い,空いたグラスを頻繁に回収するなどして少しでも接点を持とうと努めた。「うふふ…一緒にアンパングミを食べたいなぁ~」なんて妄想しながら,空いたグラスを洗うためにキッチンに戻るのだが,多部未華子の笑顔に気を取られていたため,排水溝にアツアツの油が満ちていることに気が付かず,そのままダイブしてしまった。
ジュッ!と足が素揚げされる音よりも先に,とんでもない熱さを感じ,思わず持っていたグラスを投げ出し「ア”ッーーーーーー!!!」とトムとジェリーのように叫びそうになった。

(参考動画)
しかし,そんなオチャメなムーブが許されない孤独キャラだったため,叫びをぐっと飲みこみ,素揚げされた足をゆっくりと取り出すことしかできなかった。周りの仲間は「だ,大丈夫・・・?」「ちょ,ちょっと休んだら・・・?」と私の腫れた足を見て,まるで腫れものを扱うように慎重に話しかけてきたが,「アッ,全然大丈夫ッス!(ニチャア)」とぎこちないスマイルをして,そのまま働いた。
もしもそれなりに良好な関係を築けていたら,「いや~かわいいお客さんに見とれていたらダイブしちゃったんですよね~」(HAHAHA!)と笑い話にできたかもしれないが,残念ながら,協調性のない奴が無言で油に足を浸したというヤバイ認識ができただけだったようだ。
それから,油落ちのタラオくんをいじる流れになると,「アッ‥そういえば,もう一人ヤバい奴も落ちてたな‥」みたいな流れになってしまい,徐々に油いじりはタブーという風潮になってきてしまった。ますますアウェーを極める時にあのロシアンルーレット事件が起きた。
地獄ロシアンルーレット事件
孤独を極めてきた頃,寿司屋の大将が「ワサビ入りロシアンルーレットをやろう!」と仲間たちに持ちかけた。ワサビ入りロシアンルーレットとは,人数分の寿司の中に一つだけ大量のワサビが入っていて,それを食べた人の反応を見て笑うという,絆が深まること間違いなしの超オモシロゲームだ。その時は,自分含めて4人のバイトがいた。一体誰の寿司にワサビが入るのか…!!
すると,大将はちょっと気まずそうに「あ,イソノ君もやる…?」と聞いてきた。あ,最初は人数に入っていなかったのかと思ったが,仲間たちとかけがえのない思い出を作るチャンスだと思い快諾した。
大将は4人分の寿司を握り,目の前に差し出した。1人ずつ思い思いの寿司を手に取り,「せーの」の掛け声で,一斉に寿司を口にした。一体誰の寿司に大量のワサビが入っていたのか,各々楽しそうに顔を見合わせる。
しばらくたって,不穏な空気になってきた。誰もワサビを食べた反応をしないのだ。
もう,軽く10秒は経過している。大量のワサビがあったなら,とっくに反応している時間のはずだ。
気まずくなる店内。
お前?と指をさされ,いやいやと首を振る同士(マイメン)達の顔。一体どうなってるんだ。
ふと,大将の方を見ると,気まずそうに私を見つめる目線に出くわした。
なんだ?と思っていると,口の中にほんのりとワサビの味がした。
あ,俺だったんだ…
そう,私は海鮮丼をペプシコーラと一緒に食べて彼女に振られたエピソードがあるほど舌が終わっているので,ワサビに対する反応も人より鈍かったのだ。
あまりにも時間が経ちすぎて,完全にしらけてしまった我々。いまさら名乗り出るのもおかしいとは思ったが,しかたなく,
「アッ…俺ダッタカモ…」
と弱弱しく手を挙げた。
その瞬間,シベリアよりも寒い空気が流れた。
結局,最後までみんなと距離を感じてしまった。とっても近くにいたのに,まるで薄い膜にでも覆われているように。アンパンマングミのオブラートのようだ。
最新記事 by DachimiN (全て見る)
- 【アメリカのモンスターエナジー徹底レビュー】結末に一同驚愕?!ガキが・・舐めてると潰すぞ!!! - 2021-01-03
- 地獄の免許合宿 ~外道も涙~ - 2020-10-28
- 人生で一番辛かったロシアンルーレット - 2020-08-26